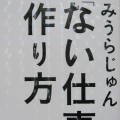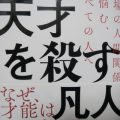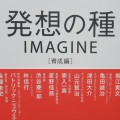読んでいない本
について
堂々と語る方法
著者 ピエール・バイヤール
これはおもしろい。
そもそも本を読んだ、
ってどういう状態なのか。
流し読みはどうなのか。
全部読んだつもりだけど、
ほぼ覚えていないとか。
人に聞いたのでだいたいわかるとか。
曖昧なんですね。
何回も書くけど、
作者と読者は違う感覚で、
違う受け取り方をするわけ。
そして、
読者同士も当然受け取り方が違う。
なので、
何を言おうが間違ってない。
自分が思ったことだから。
「内なる書物」と「共有図書館」の関係。
個人的に現段階では、ブログにタグ付けする感じですかね。人それぞれ。
内なる書物にタグ付けして、共有図書館に置く。そのタグ付けの仕方は人それぞれ違うってこと。作者の意図も関係ない。これはアートにも言えるかな。— 村山 和典 (@nori_murayama) April 29, 2020
オチにもあるけど、
子供の頃からこういう授業があった方がいいでしょうね。
前にも書いたかもしれんけど、
本の読み聴かせがいいのか。
未読座談会の話をしたかどうか忘れましたが、
あれに近いね。
この本は2007年、
日本では2008年の本ですけど。
家族で未読座談会をやることをおススメします。
教養の話が最後の方に出てくるけど、
教養と創造性って相反するのかな。
やはり知らない方がいいってことですかね。
多角的な視点に立つと、
物事が立体的に見えてくると思います。
すると、
具体的に見えすぎて、
創造する余地がなくなるってことかな。
ある程度縛りがあった方がいいって話もあるけど。
RPGみたいに。